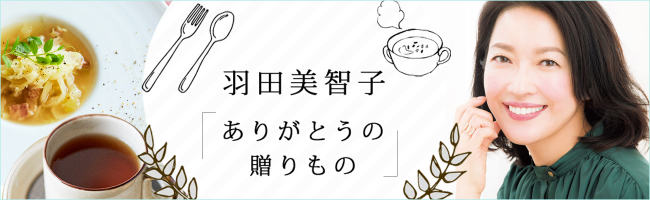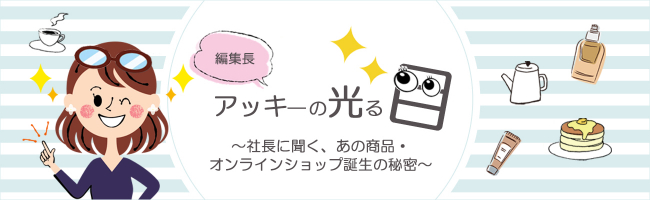400年以上の伝統を19代目が復興!一生ものの銅製酒器「仙臺銅壺(せんだいどうこ) 盃」
2025/05/12
今回編集長アッキーが注目したのは、昔ながらの手法で一つひとつ手作りされた銅製の「盃」。使い込むほどに風合いが変化し、味わいを増していく“一生もの”の道具です。作り手は400年以上の歴史を持つ仙台の企業、株式会社タゼン。19代目にあたる代表取締役社長の田中善氏に、スタッフがお話を伺いました。

株式会社タゼン 代表取締役社長の田中善氏
―御社は400年以上の歴史をお持ちだそうですね。
田中 1596(慶長元)年に銅を使った飾り金具などを作る「御銅師(おんあかがねし)」として創業したのがはじまりです。初代・善蔵はその銅細工の腕を伊達政宗公に見出され、上方(京都・大坂周辺)から仙台の地へやって来ました。私で19代目になりますが、子どもの頃の認識は「タゼンは“お風呂屋さん”」。父や祖父の代から近代化を目指し、ガス器具や浴槽、トイレなどをメインに扱う住宅関連産業の総合商社へと発展していきました。
ー時代のニーズにあわせて変化してきたのですね。
田中 現代では、銅製品に触れたことがない人が大半ですよね。その背景には、明治初期に栃木県の足尾銅山で起きた鉱毒事件があります。有害物質を含む排水が渡良瀬川に流れ込み、周辺住民に深刻な被害をもたらしました。さらに明治末期には、銅にできる緑色のサビ“緑青”が「なめると死ぬ」と噂され、教科書にも猛毒と記載されました。こうした風評被害も重なり、銅製品だけでは経営が立ち行かなくなり、事業転換を余儀なくされたのです。

「あかがね」とも呼ばれる銅は、人類が最も古くから使っていた金属のひとつ。
創業当時は神社仏閣の装飾を、
その後にはやかんや鍋などの生活道具を手がけていた。
―社長ご自身の歩みについても教えてください。高校を7日で中退されたとか。
田中 そうなんです。小・中学校の頃は優等生で、勉強も好きだったんですよ。どうして分数の割り算は分母を引っくり返して計算するのかとか、そういったことを突き詰めて考えていくのが面白くて。でも高校生になって受験勉強、つまり暗記をしてアウトプットするっていう勉強法に全く面白みを感じられなくなったんです。それで高校を中退し、全国を旅することにしました。旅といっても、あてどない放浪の旅ではなくて、会いたい人や体験したいことを求め、各地を訪ね歩いていました。その旅の中で、タゼンの祖業である銅細工の面白さに気づき、15歳で弊社に入社。銅の事業を復活させるべく力を注ぎました。
ー旅の経験はどのようなものでしたか?
田中 まず「どうすれば生きていけるか」を真剣に考えました。人が生きるために不可欠な水や食物、そしてそれを育む環境に興味を持ち、お百姓さんや農業に強い憧れを抱くようになりました。当時はまだ有機農法という言葉も一般的ではありませんでしたが、オーガニック素材を扱う人々や、自然と人間の共生を考える人たちに出会い、“食べていくこと”の本質を学びました。

途絶えかけた銅製品づくりの伝統を復活させた田中社長。
住宅関連事業を展開しながら、銅の職人「御銅師(おんあかがねし)」として
様々な銅細工、銅製品づくりに情熱を注ぐ。
―会社を継ぐ意識はその頃からあったのでしょうか?
田中 幼い頃はありましたが、中学に進学してからは「なぜ自分の人生なのに、決められた道に縛られなければならないのか」と反発する気持ちが強くなりました。ただ、人間が普遍的に行ってきた営みや長く受け継がれてきたものにはすごく興味があったんです。旅を始めて半年ほど経った頃、あるお百姓さんに「君の家は何をしているの?」と聞かれたことがあって、タゼンのことを話すと、その歴史の長さにとても驚かれました。それをきっかけに「祖業を復活させることが、自分の探している答えにつながるかもしれない」と思うようになりました。
ーそしてタゼンに入社されたのですね。
田中 はい。当時、社内に一人だけ残っていた銅専門の職人に教わりながら、技術を身につけました。1〜2年経つと、銅工芸や美術的な面にも興味を持つようになり、大学校で学び直した時期もあります。工場を立ち上げ「銅細工こそタゼンの本質」と信じて取り組みましたが、21〜22歳の頃、17代目である祖父と衝突し、独立することになったんです。法人を設立し、自ら商売を手がける経験を積みました。

工房では銅製品づくりのほか、銅細工のワークショップも開催。
銅板を木槌か金槌で叩いて、
オリジナルの平皿やお猪口、フライパンなどを作ることができる。
―独立後はどのような歩みだったのでしょう?
田中 独立して、なんとかやっていけるようになったのが、ちょうど震災前くらい。その後、結婚して、双子の女の子が生まれたんです。そのときに、子どもを産み、育て、次の世代につないでいくということは、人間の普遍的な行為そのものだなと思って。それで24時間体制で妻と一緒に子育てをしようと決めたわけです。会社は畳まず残しながら、でもオーダーは全部ストップして、専業主夫を3年間ほどやっていました。
子育ては本当に大変で、徹夜で銅細工をしても痛めたことのなかった手が、育児開始からわずか1〜2か月で腱鞘炎になったほど。精神的にも肉体的にも限界を感じたとき、住宅空間に大いに助けられていることに気づきました。トイレが唯一のプライベート空間になり、お風呂が心身を癒す場になるなど、住環境の重要性を実感したのです。考えてみると、将来どれだけコンピューターやAIが進化しようとも、こういった住環境は必ず要るわけですよね。この体験から、タゼンが銅を発祥としながらも、住宅関連事業へと進化した意味を深く理解できるようになりました。
ーそこからタゼン復帰に至ったのですね。
田中 父に頭を下げ、「銅だけでやっていこうと思っていたけれど、タゼンとしての事業も非常に普遍的で大事なものだということが分かったから、ぜひ継がせてほしい」と伝え、会社に戻らせてもらいました。それ以来、銅も住宅も、両輪で事業に取り組んでいます。

田中社長が立ち上げたブランド「仙臺銅壺」の銅製品は、
古くから人々の生活の近くにあった「銅壺」を今風にアレンジしたもの。
代々受け継がれてきた伝統の技術を使って、一つひとつ手作業で作られている。
―「仙臺銅壺」というブランドはどのように誕生したのでしょう?
田中 「仙臺銅壺」では、日常に寄り添う銅製品を多数取り揃えています。「銅壺」とは主に火鉢の中で湯を沸かすための銅製道具で、タゼンでは5〜6代目の頃から製造していました。明治期には鉄道網の発展により流通が広がり、仙台から全国へ向けて商品を出荷。そこで「仙臺銅壺」というブランド名を冠し、大きな人気を博しました。今でも東京の古い飲食店に当時製造した銅壺が残っていることがあります。

丸みを帯びたフォルムが美しい「仙臺銅壺 盃」。
銅ならではの薄く鋭い口あたりによって、
日本酒本来の香りや味わいが敏感に感じられる。
―「盃」を商品化した背景は?
田中 ブランド復活の第一弾として「せり鍋」を開発し、続く第二弾として企画したのが「盃」です。コロナ禍でお酒業界が打撃を受ける中、地元である旧仙台市内(若林区荒町)最古の酒蔵とタッグを組み、酒を楽しむための道具を作ろうと考えました。日本酒は江戸時代から、温めたり冷たくしたり、温度変化を楽しみながら飲まれてきたものですから、銅壺にも囲炉裏の熱で酒を温める燗銅壺や、外で湯煎するための酒銅壺など、酒を楽しむことを目的とした道具があるんですよ。それを復活させようという取り組みの一環として、酒器である「盃」も作ることにしたんです。
ー盃はどのように作られているのでしょう?
田中 仙臺銅壺の商品はすべて手づくりですが、この盃は「ヘラ絞り」という技法を使います。機械で回転させた銅板に鉄製のヘラを押し当て、形を作り上げる手仕事です。かつて日本が世界に誇った技術ですが、現在では東大阪や東京・大田区、新潟の燕三条など、古い町工場にしか残っていません。幸い、弊社にも長らく眠っていた機械があったため、各地の職人を訪ね歩きながら技術を学び、復活させました。

仙臺銅壺の商品は、ECサイト「タゼンドウキテン」のほか、
仙台市内にある5つの店舗で購入可能。
―銅製品のお手入れについて教えてください。
田中 普通の食器と同じく、洗剤で油分を落とせば十分ですし、食洗機の使用も可能です。ただし、銅は経年変化する素材です。水垢や指紋により色が変わったり、虹色の波紋が生まれたりすることもあります。この変化を美と捉えたのが千利休。使い込むほどに育っていく、その過程自体を楽しんでいただければと思います。
ーまさに“一点もの”に育てる喜びですね。
田中 はい。今の世の中は何でも気軽に買える、ものに溢れた時代ですけれど、自分だけの道具を育てていく価値が、いま改めて見直されていると感じます。
―本日は貴重なお話をありがとうございました!

「仙臺銅壺 盃(素)(炎)(染)」
価格:(素)¥11,000(税込)(炎)¥11,550(税込)(染)¥11,550(税込)
店名:タゼンドウキテン
電話:0120-026-837(8:30~17:30 日祝日除く)
定休日:インターネットでのご注文は24時間365日受付
商品URL:https://ec.on-akagane.com/products/sakazuki
オンラインショップ:https://ec.on-akagane.com/
※紹介した商品・店舗情報はすべて、WEB掲載時の情報です。
変更もしくは販売が終了していることもあります。
<Guest’s profile>
田中善(株式会社タゼン 代表取締役社長)
1982年仙台市生まれ。創業429年「田善(現:株式会社タゼン)」の十九代目。御銅師(オンアカガネシ)。株式会社タゼン代表取締役社長。「人間の本質」を考え高校を7日で中退。全国を旅する中、祖業の銅と出会う。子育てを通し現業のリフォームに開眼。令和元年よりあかがねプロジェクト始動。「せり鍋」「酒器」などの仙臺銅壺シリーズを発表。体験型観光など、銅の本質「伝導する力」で地域や世界と共創し、チャレンジを続ける。
<文/野村枝里奈 MC/田中香花 画像協力/タゼン>