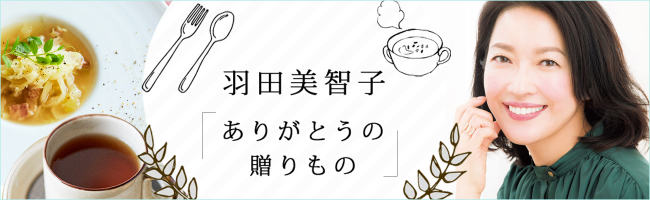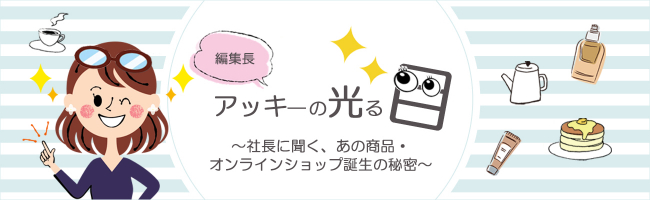使うほどに愛着がわく! 職人の手仕事による丁寧な編み込みが美しい「ペーパーコードスツール」
2025/05/08
ペーパーコードとは、北欧で誕生した紙製のひものこと。もともとは麦などの作物を束ねるために使われていましたが、耐久性が高く、見た目も美しいことから、1940年代頃より編み込んで椅子の座面に用いられるようになりました。インテリア好きなら北欧家具のデザインチェアで目にしたことがあるのではないでしょうか。今回、アッキーこと坂口明子編集長は、国産のペーパーコードを使ったナチュラルでシンプルなスツールに注目。制作しているのは、広島県の編み師こと株式会社府中家具 店舗運営責任者の飯田成光氏です。スタッフが取材をすると、制作の経緯やこだわりのほか、家具屋を中心とした町づくりへの取り組みについて、お話も伺うことができました。

株式会社府中家具 編み師 兼 店舗運営責任者
くらしと家具「HOLM230」町長の飯田成光氏
―株式会社府中家具さん、まずは御社について教えてください。
飯田 広島県で家具の販売を行っている会社で、設立は1984年、創業41年目になります。福山市にある複合商業施設「HOLM230」内で運営している「 FUCHU TENJIKAN(府中展示館)」という家具のセレクトショップを拠点に、府中家具や飛騨家具を中心とした家具類やインテリアアイテムの全国販売、オーダー家具なども承っています。

「HOLM230」内「 FUCHU TENJIKAN(府中展示館)」の外観。広大なスペースで、時間を忘れて楽しめる。
―広島県の特産品である府中家具を、株式会社府中家具で扱ってらっしゃるという…?
飯田 ややこしいですよね(笑)。もともと広島県府中市は、タンスなど箱もの家具の産地として知られ、そのルーツは300年も前にさかのぼるといわれています。歴史ある府中家具は、脈々と受け継がれてきた職人の技が細部に宿り、量産品の家具とは一線を画す高品質な製品をつくり出す、いわば家具のブランドです。高度経済成長期には婚礼家具セットが爆発的なヒット商品となり、府中家具の名は全国に知れ渡るようになりました。ですから、弊社も創業当初はタンス専門店だったんです。
―創業されたのはどなたでしょうか。
飯田 現・代表取締役である小森山卓次で、彼ももとは府中家具の工場でタンスをつくる職人でした。実家が弊社の前身にあたる小森山家具という家具メーカーを営んでおり、次男だった代表はその販売部門として独立。株式会社府中家具の名で小売業をスタートさせたのが、今の会社です。広島市の府中家具地域に製造工場も持っていたのですが、今では工場は閉めており、家具をセレクト販売する小売業を残したという状況です。

株式会社府中家具の販売の拠点となるセレクトショップ「 FUCHU TENJIKAN(府中展示館)」。
―飯田さんが入社された経緯は?
飯田 じつは私は関東の出身でして、普通に学校を出て食品会社に就職をして、サラリーマンをやっていたのですが、知り合って結婚した女性がたまたま広島の家具屋さん、株式会社府中家具の娘さんだったのです。その家具屋さんが新業態を始める、というタイミングで、まず妻のお姉さんがそこに加わることになりました。私にとって義理のお姉さんにあたるその人が、一緒にやりませんかと私を誘ってくれて、異業種に入り込んだのが2011年のことです。現在、店舗責任者としてその義姉と役割分担して店を切り盛りしていますが、当時はまさか自分がファミリーの一員になって企業の経営にかかわるとは夢にも思っていませんでした。
―新業態といいますと?
飯田 先ほどお話した弊社のセレクトショップ「FUCHU TENJIKAN」が入っている複合施設「HOLM230」のプロデュース及び施設運営になります。
“HOLM(ホルム)” とは、デンマーク語で“川辺の小さな町”という意味です。広島を代表する芦田川の川辺に、豊かな時間を過ごしていただけるような“小さな町” をつくりたいという想いからこの名を付けました。家具ショップを軸に、カフェやベーカリー、レストラン、お花屋さん、ヘアサロン、メガネショップなど、日常を豊かに彩るショップや癒やしにあふれた空間がいくつも広がっています。

毎日の散歩コースにもなるような、緑いっぱいの「HOLM230」。飯田さんはここの町長と呼ばれているのだそう。
―複合施設自体も運営されているのですね!
飯田 はい。代表の大きな構想として、家具ショップにより多くの方に足を運んでいただくために、飲食や美容、衣料といった異業種の仲間も一緒になった業態で、このエリア自体を魅力的で新しい商店街のようにしたいという思いがありました。かっこいい言い方をすれば、衣食住すべてを一か所で楽しんでいただける、そんな場所です。実店舗の生き残りをかけ、さまざまな業種の方の力を借りて、くらしと家具「HOLM230」という空間ができ上がりました。ちなみに230は、ここの住所の番地です(笑)。
―異業種の仲間集めは、どのようにされたのですか?
飯田 ここにしかないローカルな複合施設にしたい、という思いのもと、地元で頑張って活躍しているショップ主体にテナント誘致を始めました。代表がまず声をかけたのは、あるレストランだったそうです。近隣の飲食店を食事して回り、この界隈で自分自身がいいなと思ったところを一本釣り。直接お声かけさせていただきました。でもそのあとは比較的、ご縁による出会いが多かったかもしれません。「HOLM230」の取り組みに共感して集まってくださったり、ご紹介で成立したりするなど、大きく誘致活動するというよりは、自然とこのメンバーになっていった感じです。
―オンライン販売に関しては、いつ頃のスタートだったのでしょうか。
飯田 2年前の夏です。それまで頑なに実店舗での集客を広げていこうと頑張っていたのですが、コロナ禍にオンライン販売の重要性を思い知らされ、それでも人手不足を言い訳にお恥ずかしながら後回しにしていました。
ところが、ペーパーコードとの出会いが転換期となりました。ぜひこれを全国のお客さまに広めたい、認知してもらいたい、という思いにかられ、オンライン販売に踏み切ったきっかけが、今回ご紹介させていただく「ペーパーコードスツール」をはじめとしたペーパーコードチェアのシリーズです。

ペーパーコード編みのスツールの完成品が、オンラインで購入可能。軽量で耐久性も高い。
―北欧家具で見かけるデザインですが、国産でつくられているのですね。
飯田 そもそもこのペーパーコードという紙のひもをイスの座面に編み込むという手法は、海外ではずっと昔から存在していたのですが、機械化できないところがおもしろいと思っていて…。ナチュラルで温もりを感じる手編みでありながら、北欧の著名な家具デザイナーが取り入れるくらい、どこか洗練されたデザイン性もあって、私自身ずっと気になっていました。
ある時、たまたまお客さまが不要になった椅子に編み込んでリメイクしてSNSにあげてみたところ、とても反響があったんです。持ち主のお客さまからも驚きと喜びの声をいただきました。そこから、国内生産への可能性を広げていきました。

コンパクトな一人掛けで、ナチュラルな佇まいはどんなインテリアにも自然と合う。
―材料のペーパーコード自体、あまり馴染みがないと思うのですが…。
飯田 馴染みがない、そうですよね。でもじつは、百貨店などの手提げ袋の取っ手部分に紙が使われていることがありますよね。あれ、ペーパーコードなんです。めったに切れることがないくらい丈夫で、主に再生紙を使っているので環境にも配慮した素材です。
製品化にあたっては、そのペーパーコードを強く撚(よ)り合わせてもっと頑丈なひも状にしたものを、お隣の岡山県にある工場でつくってもらっています。探すと海外の製品はたくさんあっても国内でペーパーコードをつくっている工場はほとんどなかったのに、これもご縁なのか、ほぼ地元に近い場所でめぐり合うなんて、これはやるしかないと思いました。
―なるほど。では、岡山の職人さんがつくっているということですか?
飯田 いいえ。岡山からペーパーコードを仕入れて、私が座面に編み込んでいるのです。 私、編み師ですから(笑)。当初は、どこかつくってくれるところはないかと探したのですが、工業化された日本の工場ではどこからもやれない、と言われてしまって。ゼロではないかもしれませんが、国内でこうして手編みして販売しているのは、かなり少ないと思います。
でもやってみて感じたのですが、ひとつひとつ丁寧に編み込んでいく作業は、日本人に向いていると思います。座っても緩んだり曲がったりしないよう、緻密に交差しながら固く編み重ねていく手作業は、細かい日本人にぴったりですから、緩めに編んである海外のものより強度は抜群にいいですね。
樹脂加工されているペーパーコードは濡れても一旦水をはじきますし、劣化しないわけではありませんが、傷んだら編み直しすることも可能です。修理しながら繰り返し使っていただくことで、より愛着もわいていくのではないかと思います。

「こんな風に魂を込めて編んでいる職人は他にいないと思います!」と飯田さん。
―編み込む土台となるフレームや脚の部分はどうされているのですか?
飯田 例えば今回ご紹介するスツールのフレームと脚は無垢のブナ材なのですが、岐阜県の飛騨の木を使っています。岐阜県の木材協同組合で、日本の木をもっと使っていこうよというプロジェクトを推進していることもあり、国産家具のよさを感じていただくにはもってこいのアイテムだと思います。飛騨の椅子工場で、座り心地のいいサイズ感になるよう特別にフレームだけつくってもらい、そのフレームが広島の弊社に届き、座面に岡山のペーパーコードを編み込んで完成品となる、というわけです。他にフレームの素材としては地元広島のマツ、それからこちらは外材になるのですが、人気のオーク材、その3種類からお選びいただけます。

よく見るとひとつひとつ木目が違うのも、素朴な天然木ならでは。
―座面の特徴的なデザインは飯田さんご考案ですか?
飯田 これは封筒編みといって、中央に向かって三角に織り込んだような模様はペーパーコードチェアでは割と主流となる、伝統的なデザインなんです。さらにもうひとつ、縦横で交差に織り込んでいく鹿の子編みというデザインも一般的で、私はこの2種の技法を習得しています。
歴史あるペーパーコードチェアは、もともとデンマークのデザイナーが戦時中にできるだけ安価で、強度が高い椅子を、ということでつくり始めたのが起源だといわれています。それを今、日本の私が継承しているという事実には感慨深いものがありますね。
ゆくゆくはオリジナルの編み方を考えたり、コラボなどもやってみたいですが、この2種ならスツールで2~3時間、複雑なダイニングチェアでも3日ほどあれば編み終わるので、今のところ編み方はこのどちらか、形もスツールかダイニングチェアかで受注しています。
とにかく力を込めて固く編んでいるため、これまで崩れたことはありません。緩い方がやわらかくなると言われることもありますが、どうしてもひもがずれやすいんです。ずれないようにきつくテンションをかけているので、その分、長く使っていただけるはずです。封筒編みの場合は中央にくぼみができるように編むことで包み込まれるように座ることができ、座っていやな固さにはならないと思います。

縦横に何重にも交差して編み込んでいく鹿の子編みの座面デザインと、フレームの材質マツとの組み合わせ。

座面を封筒編みした、背もたれ付きのペーパーコードチェア。長時間座っても疲れにくいのが特徴。
―実際に編んでいるところを見てみたいですね!
飯田 インスタグラムに動画を投稿していますので、ぜひ見てみてください。また、じつはワークショップもやっています。実店舗の「FUCHU TENJIKAN」の店頭で、希望者のみ不定期ではあるのですが、サポートしながら編んでもらっているのです。女性の方が多く、少し大変そうにギュッギュッとやっておられますが、皆さん編み終わると楽しかった、と言って帰られるのがとても印象的です。
私たちも普段から店頭で制作しているので、通りかかった方が声をかけてくださったり、こちらからペーパーコードチェアに関するストーリーをお話したり…。「ここでこんな風につくってるんだ」「自分でもつくれるの?」「何かあったら持ってきていいのね」、などと距離感近く会話しながら販売できることで、より安心感をもって使ってもらえると思います。
―自分で編んだスツールを買って帰れるのですか!?
飯田 はい。サポートの費用はいただきますが、単にものを買ってもらうだけでなく、体験することも含めて販売するといいますか…。もちろん不具合が出てしまったら、お持ちいただければ編み直しするなど、町民同士のような感覚で相互交流できる、「HOLM230」ならではの価値を提供できたら、と考えているのです。「自宅でこんな風に使っているの」とか「編んでるところを見て購入したのよ」など、再来店してお声かけいただくこともあり、そんな時は本当に町長冥利に尽きますね。

「HOLM230」には多目的フリースペースもあり、
地元クリエイターとの出会いの場としても活用され、産業の横の繋がりを生むところとなっている。
―それでは、最後に今後のビジョンをお聞かせください。
飯田 家具事業と町づくり事業、この2本柱の強化が当面の展望になりますが、やはり最終的には地域の活性化、これが大きな目標です。こういった複合施設を運営しているからには、扱う家具類への興味をきっかけに、地元にたくさん足を運んでもらうことが大事。そのためにはさまざまな発信が必要です。ペーパーコードチェアのオンライン販売などを起爆剤として全国区的な認知度を広げ、「HOLM230」があるから行ってみたいと思わせる仕掛け、その先の変化も視野に入れます。広島県福山市という地域を活性化する担い手になりたいのです。ぜひ応援を、よろしくお願いいたします!
―家具を軸とした町づくりが、今後どのように変化していくのか、興味深く見守りたいと思いました! 本日は、貴重なお話をありがとうございました。

「国産 ペーパーコードスツール ブナ」
(サイズ:幅400×奥行300×高さ400㎝)
価格:¥24,800(税込、送料込)
店名:くらしと家具「HOLM230」
電話:0849-76-1122(9:30~17:00 水曜除く)
定休日:インターネットでのご注文は24時間365日受付
商品URL:https://item.rakuten.co.jp/holm230/308003245/?variantId=normal-inventory
オンラインショップ: https://www.rakuten.co.jp/holm230/
※ご注文いただくタイミングにより、1〜2か月ほど製作のお時間を頂戴いたします。
※紹介した商品・店舗情報はすべて、WEB掲載時の情報です。
変更もしくは販売が終了していることもあります。
<Guest’s profile>
飯田成光(株式会社府中家具 編み師 兼 店舗運営責任者、 くらしと家具HOLM230町長)
1977年、茨城県生まれ。食品会社勤務ののち、2011年に妻の実家である株式会社府中家具に入社。毎日行きたくなるような家具屋を目指し、日々奮闘中。
<文/亀田由美子 MC/田中香花 画像協力/府中家具>