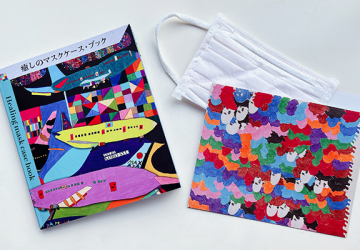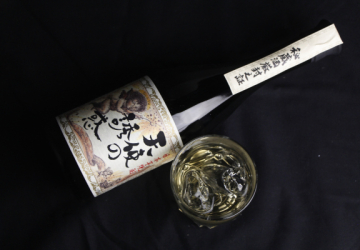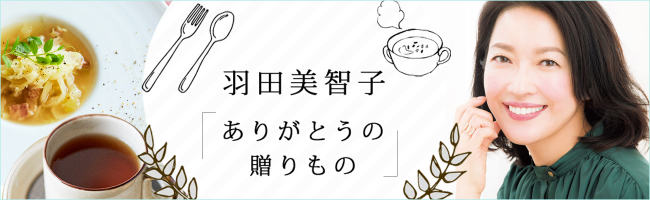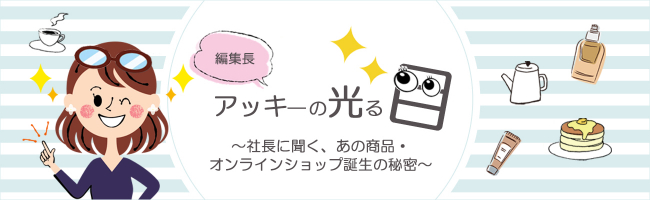伝統製法を大切に守り、日本の食文化を次代に繋ぐ、おいしい佃煮
2025/07/02
1854年の創業以来、伝統製法を守りつつ進化を遂げる佃煮店「籠長本店」。素材や調味料を厳選して手作りする「くぎ煮」には、長年のファンがいます。編集長のアッキーが注目したのは、「しらすのくぎ煮」と「やわらかちりめん山椒煮」をセットにした贈り物にもぴったりの詰め合わせ。それぞれの製法や特徴、味わいなどについて、6代目・代表取締役・籠谷茂様に取材陣がお話をお伺いしました。

有限会社籠長本店 6代目・代表取締役 籠谷茂氏

2012年に発祥の地から八代に本社を移転。アンテナショップも備え多くの顧客を迎える。
―まずはご創業から現在に至る沿革をお教えください。
籠谷 弊社の創業は江戸時代の嘉永7年(1854年)、初代長兵衛が、姫路で海産物問屋を開いたのが始まりです。その後、昭和になって4代目の正治が佃煮の製造を手掛けるようになり、1950年に法人化いたしました。4代目が明石に行ったときに郷土料理の「いかなごのくぎ煮」に出合い、あまりのおいしさにそのレシピを研究し、独自でつくるようになったそうです。その後、1967年に工場を拡張する際、より鮮度のいい材料が手に入る漁港近くのたつの市に移転。たつの市には佃煮づくりに欠かせないおいしい醤油の醸造所があったことも移転の決め手になりました。2012年姫路市八代に本社を移転し、商品を直接ご購入いただける店舗も開業しました。


より鮮度の良い材料を手に入れるべく、1967年に漁港が近いたつの市に工場を移転した。
―籠谷さまは何代目になりますか?
籠谷 6代目です。私は東京の大学に進んで経営学を学び、卒業後は老舗の漬物屋に入社、百貨店の直販店などでも経験を積みました。当時の販売経験や学びは現在の仕事に通じるところも多く、経営にも生かせています。その後、籠長本店に入社し、2005年に代表取締役に就任しました。
―現在の主力商品は「しらすのくぎ煮」とお聞きしています。
籠谷 そうですね。創業当時は、兵庫県の郷土料理でもある「いかなごのくぎ煮」をメインに製造しておりましたが、気候の変動などもあり、いかなごがほとんど獲れなくなったのです。20年前と比べると漁獲量は100分の1ともいわれています。漁期も以前は3月~4月の2か月間だったものが、昨年は1日、今年は3日間になってしまいました。そこで、その代わりにくぎ煮にできるものをと考案したのが、「しらすのくぎ煮」でした。
―くぎ煮という名前の由来は?
籠谷 生の魚は真っ直ぐなのですが、煮炊きすることによって古クギのように曲がるのです。色合いも茶色になるので、その姿からくぎ煮と名付けられたそうです。

添加物は一切使用せず、厳選した材料でつくられる「しらすのくぎ煮」。ご飯はもちろん、お酒にも合う人気商品。
―しらすに変えたことでご苦労もあったのでは?
籠谷 はい。魚の種類が違いますので、食感や持ち味も違います。くぎ煮に仕上げるために、火加減や炊き上げ時間などを変えながら試行錯誤しました。なかでも苦心したのが、火加減です。弊社では、直火釜炊き製法を用いています。これは、大きな高圧釜などで機械的に炊き上げるのではなく、熟練の職人が状態を見ながら丁寧に炊き上げる製法です。白米を直火で炊く効果と同じように、下から上へと巻き上がる調味料の対流をつくり、ふっくらとした艶のある佃煮に仕上がります。しらすは荷崩れしやすい魚なので、その時季の気温や湿度なども見て、こまめに火加減を調整しなければ、思うような食感や味にはなりません。


直火釜で火加減や時間など様子を見ながら丁寧に炊き上げる伝統的な製法。30年の経験を持つ熟練の職人だからこその一品だ。
―「しらすのくぎ煮」の特徴を教えてください。
籠谷 まずは安心安全に食べていただけること。しらすは瀬戸内産を中心に国内産のものを使用しています。添加物等は一切使用していません。魚だけでなく、生姜は香りの良い高知県産と原料にはこだわりを持って厳選しています。これらの材料は実際に産地へ足を運び、品質を確かめた上で仕入れております。変わらないのは味付けで、これは4代目の時代からの味を守っています。特に大切なのが、「うすくち生醤油(きしょうゆ)」です。これは、火入れもろ過もしない「もろみ」を絞ったままの醤油で、流通や保管が難しいため、一般的に出回ることがほとんどありません。弊社では長年のお付き合いがあるから、この生醤油を安定して使用することができるのです。
―今回ご紹介の詰合せには、「やわらかちりめん山椒煮」も入っています。
籠谷 はい。こちらも、4代目の時代から製造しているロングセラー商品です。香りの高い朝倉の実山椒を用いています。上質で小ぶりなちりめんじゃこを 香り高く希少な朝倉の山椒の実とともに 直火釜でじっくり炊きました。ふっくらとやわらかくほど良い甘辛さ、ピリッとした辛味が特徴です。

山椒の香りとピリッとした辛味が特徴の「やわらかちりめん山椒煮」。ふっくらとした食感も心地よく、箸が止まらなくなる。
―佃煮はそのまま食べる以外にアレンジも可能でしょうか。
籠谷 はい。ご飯のおともとしてだけでなくお酒も進む味わいなのですが、ちょっとアレンジいただくとまた楽しみが増えます。たとえば、冷奴に乗せて食べる、パスタにからめて和風パスタにしていただく。食パンに乗せて一緒にトーストにするなどもおいしいアレンジです。
―オンラインショップはいつ頃から?
籠谷 2019年から始めております。コロナ禍ということもあって、多くのお客様にご利用いただきました。弊社はスーパーや百貨店への卸を主力にやってまいりましたが、2012年の移転でアンテナショップ的に店舗も開き、またリピーターさまにご利用いただく目的もあり、オンラインショップも充実させました。


本店内のアンテナショップ。ここで商品を購入して、その後はオンラインショップでリピートする人も多い。
―現在、商品は何品くらいありますか?
籠谷 現時点で商品は30種類弱でしょうか。一部オンラインでは展開していない商品もあります。
―リピーターのお客様も多いそうですね。
籠谷 リピーター率が6~7割もあります。ありがたいことです。特にご高齢世代から好評をいただいております。毎年ご購入いただく方もおり、「変わらない味をありがとう」という声をいただきます。
―新商品の開発にも力をいれていらっしゃいます。
籠谷 はい。やはり佃煮という商品は、どうしてもご高齢者にファンが多く。若い世代向けに佃煮をアレンジした新商品を開発しています。開発した商品は、テスト販売を通じてお客様から直接感想などのフィードバックをいただき、反映させて改良を重ねています。
―新事業も展開されたとお聞きしました。
籠谷 2024年の12月にうどんとおでんのお店「姫路うでん」を開業しました。看板メニューは、縦13センチ、横17センチの大きな揚げの中に、うどんと、ちくわ、ごぼう天、たまご、こんにゃく、大根などのおでんを詰め込んで巾着にした「姫路うでん」です。ほかにも弊社の商品力を生かした「しらす盛りご飯」や「佃煮8種ごはん」などを提供しております。雑誌やネットニュースなどメディアでも取り上げていただき、徐々に知名度が上がっております。


2024年12月に新規事業として開業した「姫路うでん」。うどんとおでんの両方の美味しさを堪能できる。
―今後のビジョンをお聞かせください。
籠谷 老舗企業には守らなければいけない伝統もあります。けれどそれだけにこだわらず、時代の流れや今の食文化にも沿っていく必要があると思っています。ご高齢の方々は佃煮の良さを既にご存知ですから、今後は若い世代にも食べていただけるような新商品の開発、時代に沿った経営や展開もしていくべきかと思います。日本の尊い食文化をこれからも繋げていくことが一つの課題であり目標でもあります。今後も、素材の品質を維持しながら、社員一丸となって新しい取り組みに挑戦してまいります。
―貴重なお話をありがとうございました。

「詰合せ しらすのくぎ煮・やわらかちりめん山椒煮【木箱】」400g(200g×2)
価格:¥4,400(税込)
店名:籠長本店オンラインショップ
電話: 079-222-0107(10時~16時 水・土・日・祝日除く)
定休日:インターネットでのご注文は24時間365日受付
商品URL:https://shop.kagocho.com/items/97954323
オンラインショップ:https://shop.kagocho.com/
※紹介した商品・店舗情報はすべて、WEB掲載時の情報です。
変更もしくは販売が終了していることもあります。
<Guest’s profile>
籠谷 茂(有限会社籠長本店 代表取締役社長)
1974年、兵庫県生まれ。東京の大学経営学部を卒業後、老舗の漬物屋に入社し、某百貨店の直販店で活躍。その後、有限会社籠長本店に入社し、2005年に代表取締役社長に就任。佃煮という和食文化を継承しながら、時代に合わせた創意工夫を加えた佃煮や惣菜の開発に注力している。さらに、2024年12月には姫路駅近辺に飲食店(姫路うでん)を立ち上げた。
<文/中井シノブ MC/田中香花 画像協力/籠長本店>